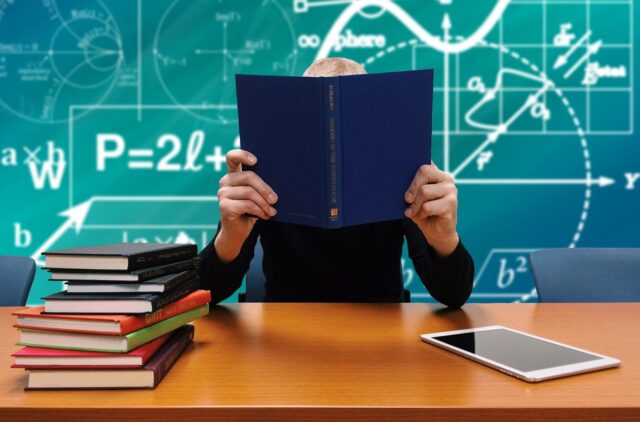- 2025-10-16
※本記事にはプロモーションが含まれています。
地方移住支援金の制度と活用法|自治体別の支援情報と起業・就職のチャンス

近年、地方移住への関心が高まり、自治体によるさまざまな支援金制度が注目を集めている。特に移住支援金は、就職や起業を目指す移住者にとって心強い支援策の一つであり、各自治体によって制度内容や金額、対象者の条件が大きく異なる。
本記事では、Uターン・Iターン・Jターンを含むあらゆる形の移住希望者に向けて、全国の自治体が実施する支援制度を詳しく解説する。さらに、地方での仕事探しや企業支援、住宅サポートなど、生活基盤を支える制度についても紹介しながら、より良い移住先の選定と支援制度の活用方法を提示する。
これから地方移住を考えている読者にとって、この記事が支援制度を理解し、最大限活用するためのガイドとなることを目指している。
地方移住支援金制度とは何か
地方移住支援金制度は、主に東京圏から地方へ移住する人々を対象に、各自治体が提供する金銭的支援制度である。この制度は、人口減少や労働力不足に悩む地域が、外部人材の移住と定住を促進するために導入している。支援の中心となるのは、就職または起業を条件に、一定額の支援金(例:最大100万円)を給付する仕組みだ。
主な特徴は以下の通り:
-
就業支援型と起業支援型の2種類がある
-
対象者の要件は自治体ごとに異なり、年齢や居住歴、就業形態などが考慮される
-
東京都23区在住者または通勤者を対象とするケースが多い
-
夫婦や子育て世帯には加算金が設けられることもある
また、各自治体はこの制度を定住施策と組み合わせ、住宅補助や子育て支援、交通費助成などと連動させるケースも多く、地域によっては手厚いサポート体制が構築されている。
地方での就職や起業に対する金銭的支援の仕組み
移住支援金制度は、以下のような具体的な就職・起業支援策と連携して運用される。
🔹 就職支援:
-
地域の求人情報サイトに登録し、対象求人へ就職した場合に支援金が支給される
-
地域に根差した企業と人材のマッチングが行われ、地元就業を促進
-
労働移動支援事業として、UIJターン人材の採用に積極的な企業が登録されている
🔹 起業支援:
-
「地方創生起業支援事業」と連動し、最大200万円の起業支援金を別途受けられる自治体もある
-
起業計画やビジネスモデルに関する専門相談の窓口が設置されている
-
地元産業の課題解決を担うスタートアップが優遇対象となるケースもある
これらの制度は、単なる金銭支援にとどまらず、移住後の生活定着を支える包括的な仕組みとして機能している。移住者はこのような制度を事前に把握し、移住先の選定材料として積極的に活用することが重要である。
自治体ごとの支援制度と対象条件

地方自治体ごとに実施されている移住支援制度は、支援内容・条件・金額の点で大きく異なる。その背景には、地域の人口減少状況や産業構造、求める人材像などが反映されている。特に地方では、市区町村単位で制度設計が行われるため、同じ県内であっても支援の中身はバラつきがある。
主な違いは以下の通り:
-
支援金の金額:一人当たり最大60万円、世帯で最大100万円の支給が一般的
-
加算条件:子育て世帯、夫婦での移住、空き家活用などにより加算される場合あり
-
対象者の要件:東京23区に在住・通勤していた者、UIJターン希望者、一定期間の居住実績がある者 など
-
就職・起業の条件:地域の指定求人への就業、地域課題解決型の起業 などが要件に含まれる
さらに、自治体によっては、住宅取得支援、引越し補助、地域活動への参加要件などを加味した制度設計がされており、制度の活用には事前の確認が必須となる。
市町村別に異なる支援金額・条件を比較紹介
以下に、代表的な自治体の制度内容を簡単に紹介する:
🔹 長野県塩尻市:
-
単身60万円、世帯100万円を支給
-
子育て世帯には加算あり
-
市の起業支援金との併用可能
🔹 岡山県津山市:
-
地元求人サイトへの就職で支援対象に
-
UIJターン希望者向けに住宅手当や交通費助成も実施
-
起業支援は地元商工会と連携
🔹 宮崎県日南市:
-
市独自の支援金制度を上乗せ可能
-
空き家バンク活用者には住宅改修費の補助あり
-
地域コミュニティへの参加が条件に含まれる
このように、地域の特徴に応じた支援内容が用意されているため、移住希望者は各自治体の公式サイトや相談窓口を活用し、自身に最も合った制度を選ぶことが重要である。
ターン希望者向けの支援情報まとめ

地方移住支援制度は、単なる引っ越し支援にとどまらず、Uターン・Iターン・Jターンなど、移住形態に応じて細かく設計されているのが特徴だ。それぞれのターンには対象となる移住者の背景が異なるため、自治体はニーズに合った支援内容を提供している。
ターンの分類と支援制度の方向性:
-
Uターン(地元出身者の帰郷)
→ 地元企業への就職支援、定住促進、地元産業の担い手支援など -
Iターン(都市圏出身者の地方移住)
→ 空き家活用支援、起業補助、コミュニティ参加支援など -
Jターン(地方出身で他の地方へ移住)
→ 地域間連携によるマッチング支援、就業体験制度、宿泊助成など
多くの自治体は、これらの移住者に対して、条件を細かく設定した支援事業を展開している。また、家族世帯、若年層、子育て世代など、特定のターゲットに向けた優遇制度も多く見られる。
Uターン・Iターン・Jターン別の支援事業と活用方法
🔹 Uターン向け支援:
-
地元企業の求人紹介サイトを通じた人材マッチング
-
ふるさと就職相談窓口でのキャリアカウンセリング
-
交通費補助や就業体験参加への助成制度あり
🔹 Iターン向け支援:
-
起業支援金やビジネスコンテストの参加費用補助
-
農業・林業体験プログラムへの参加支援
-
空き家リノベーション費用の助成制度
🔹 Jターン向け支援:
-
地域間連携事業による移住先の選定サポート
-
転職フェアや職業体験イベントの案内
-
宿泊費補助を含む短期移住体験ツアーの開催
こうした取り組みにより、自治体はそれぞれの移住者タイプに対して柔軟なサポートを提供している。移住希望者は、自分がどのタイプに該当するのかを確認し、それに応じた制度を比較・検討して活用することが重要だ。
地方での就職・求人情報の探し方

地方移住を希望する人にとって、就職先の確保は最も重要な課題の一つである。多くの自治体では、移住支援の一環として求人情報の提供やマッチング支援を強化しており、特に地元企業との結びつきを重視した地域密着型の採用支援が進められている。
また、UIJターン人材を対象とした専門サイトや相談窓口も整備されており、地方での仕事探しのハードルを下げる取り組みが活発化している。
地方就職支援の主な方法:
-
自治体が運営・連携する求人情報サイトで地元企業の採用情報を掲載
-
職業紹介事業所(ハローワーク等)と連携した就業支援
-
業種別・職種別の転職フェアやセミナーの開催
-
オンライン説明会や移住相談会による情報提供
-
若者や専門人材に向けた「人材確保支援事業」の導入
地域企業とのマッチングや人材採用支援制度の利用
地方では、都市部に比べて求人が少ないという印象を持たれがちだが、実際には多くの自治体が人材確保のための積極的な支援事業を実施している。以下に代表的な支援例を紹介する。
🔹 マッチング支援サービス:
-
移住相談窓口やキャリアコンサルタントが移住者の希望条件をヒアリングし、適した企業とマッチング
-
一部自治体では、就職先との面談交通費や宿泊費の助成も実施中
🔹 採用側への支援制度:
-
企業側に対する助成金(採用奨励金)制度あり
-
UIJターン採用にかかる人材紹介手数料の一部補助
-
長期雇用に結びついた場合の報奨金制度を整備する自治体も
🔹 情報提供の充実:
-
地方の求人情報を一元管理したポータルサイトが存在
-
業界団体と連携し、特定業種(医療・福祉・IT・農業等)の採用イベントを開催
-
オンライン上での就職説明会や相談チャットなどのサポートも充実
このような制度を上手に活用すれば、地方での仕事探しをスムーズに進めることが可能となる。特に求人情報がリアルタイムで更新される公式ポータルサイトや自治体のSNSアカウントなどを定期的にチェックすることが有効だ。
起業を目指す移住者向け補助金制度

地方移住と起業をセットで検討する人が増える中で、各自治体では移住者による地域密着型ビジネスを支援するための起業補助金制度を整備している。こうした制度は、地域経済の活性化と持続的な定住促進の両面から注目されており、条件を満たせば移住支援金と併用できるケースも多い。
特に、地域課題の解決や地元産業の振興に資するビジネスは高く評価され、補助金の対象となる可能性が高い。さらに、起業準備段階から相談や伴走支援を受けられる制度も整っており、初めての起業でも安心して取り組める環境が広がっている。
地元ビジネス支援と最大金額・助成条件の解説
🔹 起業支援金の主な内容:
-
地方創生推進交付金の一環として、最大200万円(自治体により異なる)の補助金を支給
-
移住支援金(最大100万円)との併用が可能な地域も多数
-
補助対象経費は、設備投資・広告宣伝費・事務所賃料などに限定される場合がある
🔹 支給対象となる事業:
-
地域の資源や課題を活かした観光・農業・福祉関連ビジネス
-
地元の雇用創出につながるサービス業・教育事業
-
商工会議所や起業支援センターが認定するビジネスプランコンテスト受賞者など
🔹 起業者支援のための併設制度:
-
起業相談窓口による定期的な面談・支援プログラムの提供
-
インキュベーション施設の無償貸与やコワーキングスペースの利用支援
-
ビジネスパートナーや地元金融機関とのマッチングイベントの開催
特に、地方では小規模ながら地域密着型で持続可能なビジネスモデルが求められており、事業計画の明確さと地域貢献性が審査のカギを握る。成功するためには、移住前から自治体の支援メニューをリサーチし、起業後の展望を持って準備することが重要だ。
生活支援・住宅制度などのサポート内容

地方移住の成功には、仕事や起業だけでなく、生活基盤の安定が欠かせない。そのため多くの自治体では、移住者向けに住宅確保や子育て、交通費支援など生活全般を支える制度を用意している。これらの制度は、定住促進を目的に設計されており、特に若年世帯や子育て世帯を対象とした支援が手厚い傾向にある。
支援の種類は多岐にわたり、住居探しから教育環境の整備、日常生活の相談体制まで幅広くカバーされている。移住希望者は、単なる金銭支援にとどまらず、こうした生活サポート制度の充実度にも注目する必要がある。
地方定住に役立つ住宅補助・子育て支援・交通費助成
🔹 住宅補助制度:
-
空き家バンクを活用した賃貸住宅の紹介と家賃補助
-
住宅取得支援として、新築・中古購入時の助成金制度
-
住宅改修費の補助(上限あり)、耐震・断熱対応工事への助成など
🔹 子育て・教育支援:
-
保育園や幼稚園の入園支援金や、保育料の一部助成
-
中学生以下の医療費無償化(自治体により異なる)
-
学習支援や部活動支援を通じた子育てしやすい環境整備
🔹 交通費・移住準備支援:
-
移住前の現地見学ツアー参加費や宿泊費の一部補助
-
引越し費用の助成制度(上限あり)
-
公共交通機関の定期券割引制度や通学支援など
さらに、多くの自治体では生活相談窓口が設置されており、住居探し・子育て・地域活動参加などあらゆる生活面での相談に応じている。これにより、移住者が孤立することなく地域に溶け込む支援体制が整備されているのも大きな魅力だ。
全国の自治体が実施する注目の移住支援金制度

現在、全国各地の自治体がさまざまな工夫を凝らした移住支援金制度を展開している。人口減少や地域産業の担い手不足といった課題に対し、各自治体は独自の支援内容と施策で移住希望者を受け入れようとしており、その取り組みは年々充実している。
特に注目すべきは、地方創生テレワーク交付金や地域おこし協力隊との連携支援制度など、国の制度と自治体独自施策の組み合わせによって、より柔軟かつ実効性のある支援が実現されている点である。
最新情報の確認と移住希望者への応援事業紹介
以下に、2025年時点で特に注目されている自治体の支援事例を紹介する。
🔹 北海道・東川町:
-
単身者60万円、世帯100万円の支援金に加え、住宅取得補助制度あり
-
クリエイターやテレワーカー向けの支援事業を実施中
-
地元企業とのマッチングイベントを定期開催
🔹 山口県・萩市:
-
UIJターン就職者に対し、移住支援金+就職奨励金をセットで支給
-
地域活動参加を条件にした追加支援制度もあり
-
空き家リノベーション事業と連動した住宅補助が人気
🔹 宮崎県・小林市:
-
地方での起業支援が非常に手厚い自治体として評価
-
最大200万円の起業支援金+生活支援として交通費・引越し費用補助
-
「こばやし暮らし」サイトで情報を一元提供し、相談窓口も充実
こうした自治体の支援制度は、国の方針に基づきつつも、地域の特性や人材ニーズに応じて柔軟に設計されている。移住希望者にとっては、これらの制度を比較・検討し、自分のライフスタイルや働き方に合った最適な移住先を選ぶための重要な情報源となる。
最新の支援内容は、各自治体の公式ウェブサイトや移住促進ポータルサイトに随時掲載されており、定期的な確認が推奨される。
地方移住を成功させるための活用ポイント

地方移住をスムーズに、そして後悔なく進めるためには、制度の「申請」だけでなく、「活用」する姿勢が重要である。各自治体が提供する支援策は多岐にわたり、それぞれ条件・対象・内容が異なるため、単に金額だけで判断せず、自分に合った支援と移住先を見極めることが求められる。
加えて、情報収集→相談→体験→定住という流れを意識した準備が、移住後の失敗を避ける鍵となる。
サイト活用・相談窓口・生活体験イベントの利用法
以下のような実践的な活用ポイントを押さえることで、地方移住はより現実的かつ前向きな選択肢となる。
🔹 専門サイトやポータルの活用:
-
「移住支援ポータル」「ふるさと回帰支援センター」など、移住情報が集約されたサイトを積極的に活用
-
各自治体の移住専用ページでは、支援制度・空き家情報・就職支援が詳細に掲載
-
「先輩移住者の声」などの実体験に基づいた情報も参考に
🔹 相談窓口の利用:
-
自治体の移住相談窓口や、東京・大阪などにあるサテライトオフィスを活用
-
仕事・住まい・教育・起業など多方面の質問にワンストップで対応
-
必要に応じてオンライン面談も可能
🔹 現地体験イベントへの参加:
-
お試し移住体験ツアーや短期滞在プログラムへの参加で、リアルな生活環境を体感
-
地元住民との交流イベントで地域との相性を確認
-
宿泊費や交通費が補助されるケースもあり、参加ハードルが低い
情報を「調べる」だけでなく、「比較・体験・相談」まで一貫して行うことで、支援制度を最大限に活用した地方移住の実現が可能になる。特に、地方では表に出にくい求人情報や補助金制度も多く存在するため、相談を通じた非公開情報の入手も視野に入れたい。
地方移住と支援制度の活用で広がる新しい暮らし方

地方移住支援金制度は、単なる「引っ越し費用の補助」ではなく、就職・起業・子育て・定住支援など、地域での暮らしを総合的に支える仕組みである。全国の自治体が、それぞれの特性や地域課題に合わせて、手厚い支援内容を設計しており、移住者のニーズに応える柔軟な制度が整いつつある。
特に注目すべきは、以下の3点である:
-
各自治体の制度の違いを把握することの重要性
-
ターン別(U・I・J)で支援が細分化されていること
-
求人・起業・住宅など生活全般を対象とした包括的支援があること
また、情報を調べるだけではなく、現地の相談窓口の活用や体験イベントへの参加を通じて、リアルな生活像を描くことが成功への鍵となる。
これから地方移住を目指す人々にとって、本記事が最適な制度の選定と支援の活用につながる実践的なガイドとなれば幸いである。**「希望する暮らし方」**を実現するための第一歩として、ぜひ自治体の支援を積極的に活用していただきたい。
FAQs

地方移住支援金は誰でも申請できますか?
Answer:
いいえ、原則として東京23区に在住または通勤していた者が対象です。加えて、指定求人への就職や地域課題解決型の起業が条件とされる場合が多く、自治体ごとに細かな要件があります。
支援金の金額はどれくらいもらえますか?
Answer:
基本的に単身者で最大60万円、世帯で最大100万円が支給されます。ただし、子育て世帯や条件加算がある自治体ではさらに支給額が上乗せされる場合もあります。
起業を希望する場合、どのような支援がありますか?
Answer:
自治体によっては、最大200万円の起業支援金が支給されるほか、専門家によるビジネス相談・施設利用補助・創業セミナーなどが提供されます。申請には事業計画書の提出が必要な場合があります。
地方での就職はどうやって探せばいいですか?
Answer:
各自治体が運営する移住・就職支援サイトや、UIJターン専門の求人ポータルを活用するのが一般的です。また、移住相談窓口やハローワークでも情報提供が行われています。
支援制度を最大限活用するにはどうすればいいですか?
Answer:
まずは自治体の公式サイトで制度内容を確認し、オンラインや現地の移住相談窓口に相談することが重要です。また、体験ツアーや移住イベントに参加して、現地の雰囲気を実際に感じることも効果的です。
-
【35歳までのキャリアを変える、最後の切り札】「学歴フィルター」を打ち破り、最短3ヶ月で国内MBA/MOT合格を実現する超効率的メソッドとは?
-
転職活動の先延ばし理由を解消!キャリアを活かす方法をご紹介